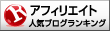巷に溢れるエコノミスト(経済専門家) の書籍を読むと、人によってだいぶ意見が違う場合があって、どれが本当なの? ってなるんですよね。
例えば、貿易取引など実需の取引は10%程度なので、残りの90%を占める投機筋が為替を動かす。と書いてあるのを読んで、なるほどそういう見方をすれば確かにそうだな。と思いました。
ところが、ある人は、「世に言われる投機筋はそもそも存在しない。」と言われる。これはどういうことか? これについて今日は書いていきたいと思います。
なお、あくまでも私の解釈なので、1つの考え方としてみてくださいね。
Contents
為替相場は需要と供給のバランスで動く
まず為替の需要供給とは、
- 通貨を買いたい(需要増)・・・通貨高へ
- 通貨を売りたい(供給増)・・・通貨安へ
というのが基本的な構図かと思います。
そしてこれらが発生する理由は大きく次の2つがあります。
実際の需要(実需)は大きく2種類ある。
貿易取引
貿易決済に使われる通貨の割合は次のようになっています。
- 米ドル・・・約40%
- ユーロ・・・約16%
- 日本円・・・約11%
- 英ポンド・・約6%
※三井住友アセットマネジメント調べ(2017年)
このブログでも過去書きましたが、日本がアメリカから何かを輸入して決済を米ドルでする場合、あらかじめ米ドルを用意します。逆に輸出した場合米ドルで支払いを受けます。そして円へ。その際為替取引が発生し、相場に影響します。
- 円を売って米ドルを買う・・・ドル高
- 米ドルを売って円を買い戻す・・・ドル安
資本取引
一言で言うと、異なる国同士のお金のやりとりですが、次の2種類あります。
直接投資
- タイに工場を建設する。
- 海外の企業に経営参加のため株式を取得する。
など。
私も関わった事がありますが、タイに工場を作る例でいうと、日本円をタイバーツに交換するために為替取引を行います。そのお金で、工場を建設したり、雇用した社員に給料を払ったりします。これを「対外直接投資」と言いますね。
こういった事がたくさん行われた結果、タイが直接投資を受け取った額から支払った額を引いて黒字の場合、タイの受け取った額が大きのでタイバーツ高、円安傾向になると考えられます。逆ならタイバーツ安、円高ですね。
間接投資
- 外国の国債や株を購入し、その売却益などを得る目的のもので、実際に工場を立てたり、経営に参加したりしないもの。
例えば、アメリカの人が日本国債を買おうと思ったら、ドルを円に変える必要があるので、為替取引が発生します。
これも直接投資と同じように、国全体で受け取った間接投資の額から支払った額を引いて黒字なら円高、ドル安傾向になるでしょう。
ちなみに日本の場合、外国への投資も外国から日本に対する投資も直接投資の方が間接投資を上回っている感じですね。
投機取引
短期的な売買を繰り返して利益を狙う人たち全般。例えば個人でのFX取引などがそうですね。
組織的なものでは ヘッジファンドですね。
ヘッジファンド
お金持ちの個人や、銀行、保険会社からお金を集め、デリバティブ。例えば気候の関係などで農作物の収穫が悪そうだと予想し場合、あらかじめオプション取引市場で “半年後に今の価格で買える権利” を確保しておく事で将来その時が来た時、その権利を高く売る事で高い収益を狙う会社。
為替相場を動かす要因はヘッジファンドなどの投機筋じゃない?
さて本題です。
最初に書いた「貿易取引など実需の取引は10%程度なので、残りの90%を占める投機筋が為替を動かす。」
が勘違いという根拠です。
結論から言いますが、上でいう90%(80%)の投機筋というのは実はスワップ。つまり、資金取引(貸し借り)なので相場の変動には関係ない。という事です。
スワップ取引
例えば変動金利の借金と固定金利の借金を交換するなど。会社の経営者が、金利が上がる事で借金の返済が苦しくなるのを嫌がって、固定金利に変えたい場合などですね。
FX取引を例に説明すると、
- 証拠金(担保)をFX業者の自分の口座に預ける。
- そのお金で通貨を借りる。
- 借りた通貨を売却する。
- 差分が利益になる。
積立FXでも同じですが、実際には借りているのに、「購入」と表現されているので紛らわしいですね。
実際外貨でお金を引き出す事はできません。借りてるだけだからですね。
重要な事はスワップ取引は為替取引(売買)ではない。貸し借りだ。という事。
売買でない以上、相場の変動にはなんの関係もありませんよね?
そして年間のスポット取引(通貨を売買することを契約した日から2営業日後に受け渡しをする外国為替取引)とスワップは日銀が合計で為替出来高として発表するため、誤解してしまう事がある。という事らしいです。つまり8~9割くらい水増しされているという事ですね。
真実は、実際に為替相場を動かしているのは、実需と生保などの機関投資家であるという事です。
やはり正攻法で、実需筋、輸出入や機関投資家のリスク・ヘッジ(先物取引、オプション取引、スワップ取引)を追って行くのが良さそうですね。