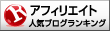株取引を始める段階で、いきなり勉強なしに取引を開始する方もおられますが、ある程度勉強してから。という方も多いかと思います。
私もその口で、Zaiの発刊する書籍を読んだり、ネットで勝っていそうな人の記事を読んだり、おすすめ本を読んだりいろいろしました。
具体的には、ファンダメンタルズ分析とか、テクニカル分析などです。
しかし、そういった本は結構なヴォリュームがあるわけです。
読むのが大変なんですよね^^;
そこで今日からその中でも決算書の読み方について、シリーズで簡潔に書いていこうと思います。
さっと読んで、まずは全体の概要を掴んでしまいましょう!
1回目のテーマは「売上高」です。
よろしくお願いします!
Contents
決算書を読むメリット
決算書を読めるとその会社の経営状態をいろいろ想像することができます。
その決算書は主に3つあります。
- 損益計算書・・営業活動の状況が分かる
- 貸借対照表・・資金調達の状況が分かる
- キャッシュフロー計算書・・営業、投資、財務のお金の流れが分かる
損益計算書でどれだけ儲かったか? などの業績を見て、貸借対照表で会社の資産がどうなっているか? 例えば、負債がどのくらいで、手持ちの現金がどのくらいなどが分かり、キャッシュフロー計算書でお金が会社でどう動いたか? を見ることができるわけです。
これが会社の成績表となり、投資家の投資判断の参考になるわけですね。
これの良し悪しだけで、絶対株価が上がるとか下がるとかは言えないわけですが、明らかに危ない経営をしている会社を避けることは可能だと思うし、年ごとの成長率などから将来有望な会社かどうかも判断ができるので、これを見ることはとても重要な訳です。
いったんまとめると、決算書から対象の会社が
- 儲かっているか?
- 倒産しないか?
- 成長し続けているか?
の3点が分かるわけです。
決算書の発行のタイミング
大きく分けて決算には、
- 四半期決算
- 中間決算
- 大決算
とあります。
四半期決算
1Q 2Q 3Q 4Q と表示されているのを見たことがあるかもしれません。
これは、1年の総まとめ(大決算)が3月だとすると、
- 1Q・・4月〜6月
- 2Q・・7月〜9月(中間決算)
- 3Q・・10月〜12月
- 4Q・・1月〜3月(大決算)
このように1年を4分割してそれぞれの期間の進捗を発表するものです。
中間決算
1Q+2Qの業績です。
大決算
1Q+2Q+3Q+4Q=通気の業績です。
原則 2ヶ月以内に決算書を税務署に提出する義務があります。
ちなみに予算が100%とすると、各Qで25%ずつ積み上げて行けば達成となりますね。
売上高をさっと見てみる
売上高は決算書の一番最初にみるところですね。
上の例の場合、△4.4%の計算方法は、5,891÷6,161×100=4.4%
となります。前期比ということです。この場合売上高は減少していますから、マイナスということですね。マイナスは△で表示されます。
売上高は本業で稼いだ金額のみをいう
売上高は商品又はサービスなどを売って、どれだけ稼いだか。をいいます。
ところが、会社は本業以外にも収益が発生することがあります。
保有土地の売買とか、株の売買などです。
そういったものは売上高として計上されません。
これを営業外収益ともいいますね。これもいずれ取り上げます。
銘柄選びの際、売上高で何を見ればいいのか?
よくある式を一応書くと、
売上総利益(粗利)=売上高−売上原価
となりますが、
売上総利益の比率が売上高に対して高いほど、付加価値の高い商品を提供しているということになります。
例えば、高くても買いたい!! と思う人が多ければ高くても買う人が多くなるので売上総利益は上がるでしょう。
例えば競合が真似できないような商品だとか、ブランド品ですね。
サービスのブランディングということもありますよね。
例えば有名人が推薦している商品です! 有名ドクターが推薦しているサプリです! みたいな。そういうのも付加価値ですよね。
付加価値というと、「のれん」というのを聞いたことありませんか?
これはちゃんと無形固定資産として計上されるものです。
要は看板代です。
例えば有名ラーメン店が屋号を受け継いで営業するあれですね。
有名ラーメン店というだけで、お客が来てくれますよね?
商売をする上での優位性とも言えます。
最近だと、Zホールディングスが買収したZOZOがのれん3,000億円の計上の話がありましたね。
そんだけの価値がないとの見解もありますが。。。
ちなみに売上原価とは、仕入れにかかったお金とか、製造業なら製品を作るのにかかった人件費、材料費、光熱費などですね。
まとめると、
- 本業で稼いだ売上高から製造コストや、仕入れコストなどの売上原価を引いた物を売上総利益(粗利)という。
- 売上総利益の比率が売上高より高いほど付加価値の高い商品やサービスを提供しているので、企業として優秀である。
補足ですが、ものすごく安く仕入れて、それなりの価格で売れた場合も売上総利益は上がりますね。
あと、技術革新などで、大幅なコストダウンに成功した例もそうですね。
さて、次回はこの売上総利益から販売費及び一般管理費を引いた営業利益の話です。
よろしくお願いします。
ではまた^^